物性実験II
結晶構造物性
http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/lab/kimura/
教員
| 教授(兼任)/佐藤 卓 | |||
| 助教/山本 孟 HP |
研究について
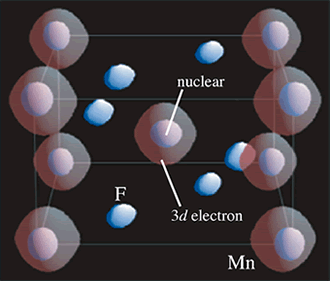
結晶は原子が規則的に並んだものですが、相転移(例えば黒鉛がダイヤモンドになる等)が起こると原子や電子の分布は何らかの事情で変化します。それがたとえ僅か0.1Å以下の変化であっても結晶の性質(誘電性、伝導性、磁性など)が大きく変わることがしばしば起こります。このような原子や電子の変位をX 線や中性子線などを用いた回折実験で「観る」ことにより、結晶の世界の法則を明らかにしていきます。実験は高温から極低温、あるいは高圧下など様々な条件で行います。こういうといかにも日常とは全く無縁なことと思えるかもしれませんが、皆さんが日頃使うテレビ・パソコンなどの中のコンデンサ、半導体など様々な工業材料の物性を理解する事や、ロボットのアクチュエータ、フラッシュメモリの材料、超伝導などの未来の物質の探索、更には地震機構の解明などとも繋がっています。結晶中の原子や電子の分布を知ることは全ての領域の基礎です。なぜなら、どの結晶でもその中には膨大な数の原子や電子が互いに影響を及ぼし合っていて、それらの相互作用が物質全体の性質を決めているからです。 実験では色々な装置を利用します。実験室には世界的にも極めてユニークなX 線回折装置があり、現在も様々な新しい装置を開発しています。
実験では色々な装置を利用します。実験室には世界的にも極めてユニークなX 線回折装置があり、現在も様々な新しい装置を開発しています。更に、高輝度放射光施設SPring-8 やPhoton Factory のX 線回折装置、そして日本原子力研究開発機構・東海3号炉の中性子回折・散乱装置を利用した、最先端の実験及び装置開発も行っています。
・研究室の主要研究テーマ
- 放射光施設(SPring-8, Photon Factory)、中性子施設(JRR-3M)、実験室での実験手法・新しい装置の開発。
- 多重極端条件(高圧、高電場、高磁場、極低温) 下での精密構造解析手法の開発。
- 水素結合型誘電体や酸化物誘電体の相転移機構の解明。
- 磁性体の磁気構造の解明、及びスピン密度分布の可視化。
- 電気伝導物質(酸化物超伝導体や有機導体など)の相転移機構の解明。
- 磁性と誘電性が共存した物質(マルチフェロイック物質) の相転移機構の解明。
